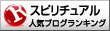九州ミステリーツアー 2 邪馬台国
今回の九州旅行では、熊本県と長崎県をまわりました。
長崎県は、島原半島を調査しました。
私が研究している古代史は、今までになかった画期的な切り口だと思います。
誰もやったことのない、「宇宙考古学」と「地上絵」を組み合わせて、日本の古代史を考察するというものです。
こういう誰も切り開いていない境地に、最初に足を踏み入れるのは、男として、最高の快感です。
この知のゲームは、とても楽しいです。
やはり、男というものは、いくつになっても、冒険者なのだと思います。
この旅行記は、前回の「古代日本ヒルコツアー」の続編のようなかんじになります。
ですから、まだ、この旅行記を読んでいない方は、そちらを先に読むと、内容をより理解することができると思います。
旅行中は、不思議なシンクロが山ほど起こりました。
まず、羽田空港から熊本空港に行くときに、JALの出発ロビーの近くで、朝食を食べようとしたら、面白い絵が目に飛び込んできました。

どこからどう見ても、「ヒルコ」でしょう。

今回の旅行も、「ヒルコ」に導かれた旅になりましたが、それは、これから、ゆっくり書いていきますね。
早朝の羽田空港です。

いつものように、時系列ではなく、テーマごとに書いて行きますので、実際に回った順番とは前後します。
ここでまた、ちょっとだけ、今までの内容を、おさらいしましょう。
この地図を見てください。

これは、江戸時代の初期に描かれた、「日本地図」だそうです。
まず、目につくのは、「四国」の位置が、かなりズレているということ。
さらに、「中国地方」の中で、特に、「山口県」のあたりが、ねじ曲がっていること。
「沖縄本島」が九州に近く、北海道が小さく描かれていることです。
大半の学者は、
「当時の測量技術が未熟だったために、ヘンテコな地図が作成されていた」
と言って、笑って終わりにしているそうです。
しかし、本当にそれだけでしょうか?
江戸時代の前から、日本には、平城京や平安京を設計して町を建築した、とてつもない技術があったのですよ。
私は、
「この地図は、ほぼ正確に描かれた、当時の日本列島だろう」
と、考えています。
おそらく、邪馬台国の時代から、江戸時代の中期くらいまでは、日本列島の姿は、こういう姿だったのだと思います。
そう考えると、とても面白いことが、わかったのです。
もう一度、上記の地図を眺めてみてください。
何かに見えませんか?
「馬」だと思いませんか?
「九州」が、「馬の頭」。
「鹿児島」のあたりが、「口」ですね。
「本州」が、「馬の身体」。
「紀伊半島」が、「馬の前足」。
「房総半島」と「伊豆半島」が、「馬の後ろ足」。
「北海道」が、「馬の尻尾」。
こういう視点で、眺めてみてください。
この絵には、「馬」だけしか描かれていません。

この地図に、「四国」を「馬が前足をのせている台」として付け足して、イメージしてみてください。
それから、もう一度、この地図を眺めてみてください。

わかりましたね。
そうです。
「台に前足をのせている馬」
これが、この地図なのです。
「馬が台の上にのって、牙をむいている国」
これが、「邪馬台国」という国の名前の秘密だったのです!
「邪馬台国」
これは、当時の日本列島の形を、そのまま描写した意味だったのです!
これに気が付いた瞬間、大感動しました。
これが凄いのは、この日本列島の姿は、山の上からでは、絶対に見えないということです。
人工衛星の高度くらいじゃないと、目視できないのです。
これ自体が、「宇宙人実在の証明」になるのです。
ちなみに、「邪」の文字の左側は、「こざとへん」ですね。
これは、象形文字だそうです。
「丘」や「盛り土」を意味するそうです。
「岩のない土だけの山」というニュアンスだそうです。
横にすると、こういう形です。
「前方後円墳」や「王国」の意味です。

あとは、この「馬」が、口から吐き出して、産んだような島が、「沖縄本島」を含む、「南西諸島」ですね。
他にも、この地図では、「対馬列島」も、ボンヤリと描かれていますが、この島の名前も、ずっと疑問に思っていましたが、これも解けました。
「馬に対面している島」という意味だったのですね。
ようやく、意味が繋がりました。
もう一度、まとめた結論を言いますね。
「邪馬台国とは、昔の日本列島の全てのエリアのことを、そう呼んでいた」
ということです。
特に、この「馬」の地図では、「九州」が「頭部」になり、「関西」が「心臓部」になることから、この二カ所は、重要な拠点だったことがわかります。
賢明な方は、私の言いたいことに、だんだん気が付いてきたと思います。
これらの話の流れから、
「日本列島そのものが、意識をもった生命体であり、言い方を変えると、超知性体でもあり、未来の生き物である。すなわち、UFOである」
こういう超大胆な仮説も、導き出されるのです。
日本の国土それ自体が、超巨大な母船であり、UFOだということです。
歴史の古い神社に行くと、「台の上にのっている馬」の銅像や石像が、よくありますね。
一昨年に行った、長崎県長崎市内にある、「諏訪神社」の写真です。
大きな「神馬像」ですね。

こういう「台に載った馬」の像があるところは、古代において、「邪馬台国」の拠点だった重要な土地なのです。
「馬」も大事だけど、下の「台」も、それ以上に重要な意味があったのです。
どおりで、これほど、立派な石の台だったのですね。
「どうして、こんな立派な台なんだろう?」
と、疑問に思っていましたが、理由が分かった嬉しいです。
これは、昔から大論争されてきた、「邪馬台国論」に終止符を打つような、ファイナルアンサーだと思います。
結論は、
「日本列島全てが、邪馬台国だった」
ということです。
おそらく、双子だった「ヒルコ」と「ヒルメ」が、それぞれ、「九州」と「関西」に行き、それぞれが、二つの都をつくったのだと思います。
だから、「九州説」も「関西説」も、どちらも正しいということです。
私は、基本的な地上絵の解釈として、大きな地上絵ほど、高次元にいる神獣が、この3次元の世界に降りてきて、物質化したと考えています。
この「馬」の地上絵は、日本列島の大半をカバーしているので、かなりの高次元から降りてきた神獣だと思います。
今回の旅で調査した「島原半島」は、この「馬」の地上絵の「目」の部分に相当します。
ということは、やはり、このエリアは、日本において、とても重要な土地だったということがわかります。
地上絵は、日本中に無数にあり、「馬」の地上絵は、関西にもあります。
何度も紹介していますが、これです。
長野県のフォッサマグナを中心に、南北を逆にした日本地図です。

「東日本」が「鹿」で、「西日本」が「馬」ですね。

これは、伊勢神宮や天皇家も、昔から知ってた地上絵みたいです。

つまり、こういうことです。
「九州を頭にした馬の地上絵」
「西日本の馬の地上絵」
このように、日本列島には、「大」と「小」の「2頭の馬」の地上絵があるということです。
さらにシンプルに言うと、
「2頭の馬の親子」
これが、「西日本」、特に「九州」を中心にした、「邪馬台国」のシンボルだということです。
驚いたことに、長崎県の島原半島には、その痕跡が見事に残っていました。
訪れたのは、「馬頭観音 中原神社」という神社です。


境内には、「馬」の彫刻が、たくさんあります。


「台の上にのっている馬」ですね。


これに、一番感動しました。
見てください!
「2頭の馬の親子」です。

このシンボルマークは、「コンパス」と「分度器」と「定規」だと思います。
つまり、「古代フリーメーソン」のシンボルです。
「エンキ」のグループですね。

大感動の中、記念撮影しました。
そして、この神社の名前、「馬頭観音」の正体は、「二頭の馬の地上絵」だったということです。

さらにスケールを広げて、宇宙考古学的な解釈をすると、「邪馬台国」のシンボルである、「馬」は、「馬首星雲」からやってきた宇宙人グループも、関わっているようです。
「馬首星雲」です。

「ウキペディア」によると、こういう説明です。
「馬頭星雲(ばとうせいうん :Horsehead Nebula)」は、オリオン座にある暗黒星雲である。
オリオン座の三ツ星の東端位置する。
その名前の通り、馬の頭に似た形で、非常に有名な星雲で、散光星雲IC434を背景に、馬の頭の形に浮かびあがって見える。
この星雲は、巨大な暗黒星雲の一部である。
1888年に、ハーバード大学天文台の写真観測によって、初めて発見された。
つまり、「オリオン座」の宇宙グループだということです。
面白いですね。
興味深いのは、九州を頭にした「馬の地上絵」は、「五島列島」を「角」にすると、「一角獣(ユニコーン)」にも見えます。

「角のある馬」、つまり、「一角獣(ユニコーン)」ですね。

さらに、面白いのは、「五島列島」の形です。
「細長い島々」の先に、「五芒星(☆)」の形に見える島がありますね。

これは、「魔法使いの杖」にも見えます。

杖の先に、「五芒星(☆)」があるのが、わかりますか?

実は、ヨーロッパの「バチカン市国」にも、これがあるのです。

上記のような一般的な普通のバチカンの写真では、わかりませんが、そのエリアを広げた航空写真だと、その正体がよくわかります。

「バチカン」のレイアウトは「鍵型」だったのです。

1550年の地図の時点で、既にそうだったみたいです。
だとすれば、年代的に、レオナルド・ダヴィンチも、このことを当然知っていて、この建築に関わっていたと思います。

近くの「サンタンジェロ城」や「ウィトルウィウス人体」との繋がりも、面白いです。
その鍵は、先の形が、「五芒星」ですね。

つまり、「バチカン」のバックにいる存在たちは、古代からの「魔法使い達」だということです。
バチカンの鍵は、「スターゲートを開ける鍵」だとも噂されているようです。
だとしたら、「五島列島」も、同様にそうだということですね。
では、その鍵穴は、どこでしょうか?
私は、それは、日本の全ての「前方後円墳」なのではないかと思っています。
鍵穴の形ですね。

まとめます。
「五島列島」=「魔法使いの鍵」
「バチカン市国」=「魔法使いの鍵」
このように、「日本」と「バチカン」には、昔から、同じ形の鍵の地上絵があるということです。
日本に、その中でも特に長崎県に、ヨーロッパから、宣教師が来て滞在していたのは、この二つの鍵に、秘密があるかもしれません。
最近、さらに面白いことに気が付きました。
江戸時代までの古地図を見ると、
「邪馬台国のシンボルは、馬だった」
そのことが、よくわかりますね。
実は、もう一つ他の解釈もできるのです。
もう一度、古地図を見てください。

この時代、なぜか、沖縄や奄美などの琉球諸島が、鹿児島に近いのですが、これは、長い鼻、つまり、「象」にも見えます。
インドの神様、「ガネーシャ」でもありますが、実は、「沖縄を含めた日本」の意味だったのです。
つまり、
「琉球諸島を加えた邪馬台国のシンボルは、象だった」
という仮説が、浮かび上がってくるのです。

今回の旅では、熊本県山鹿市の「一つ目神社」という神社にも、立ち寄りました。


「一つ目」の神様です。
「エンキ」ですね。

拝殿です。

ここには、この「馬」と「一角獣」の二頭の彫刻が彫られていました。
凄すぎますね〜



もう一度、まとめますね。
沖縄のない日本が、「馬」で「邪馬台国」。
沖縄のある日本が、「象」で「ガネーシャ」。
こういうことです。
日本中の神社にある、「象」の彫刻の本当の意味は、
「琉球王国(沖縄)を含めた邪馬台国」
だったのです。


さらに面白いことに、気がつきました。
象の鼻の先端が、「那覇」ですね。
もしかしたら、「鼻(はな)」を逆から読んで、「那覇(なは)」という地名になったのかもしれません。
「那覇」=「邪馬台国の南端」
こういうことです。
ちなみに、私は、那覇市の「開南」という土地で生まれました。
南の「鼻(花)」から、新しい日本を開国するのが、自分の使命かもしれませんね。
いや〜、やはり、地上絵は楽しいなぁ〜
余談です。
この神社の本殿には、珍しく四方に鳥居がありました。
これは、「補陀落渡海」の舟の意味だと思います。



やはり、本殿の隣には、「熊野神社」の祠がありました。


「九州ミステリーツアー」、まだまだ続きます。
次回もお楽しみに!
☆私の著書、「地球を創った魔法使いたち」も、絶賛発売中です。
ぜひ読んでみたください!
☆記事の感想などは、下記のアドレスに、お気軽にメールくださいね。(お手数ですが、メルアドは、コピーして貼り付けてください)
toma_atlas@yahoo.co.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
☆ランキングにも、参加しています。
記事が面白かったら、応援クリックもお願いします。
☆下記が、私のメインサイトの「精神世界の鉄人」のエッセイ集です。
不思議な体験談や精神世界の探求が、たくさん書いてあります。
現在は、ほとんど更新していませんが、遊びにいってみてくださいね。
http://www.tomaatlas.com/library.htm
☆フェイスブックもやっています。
☆インスタグラムもやっています。
☆ツイッターもやっています。
☆私が自信をもってオススメする、ヒーリンググッズの王様、「不思議なペンダント・アセンション」のサイトです。
http://triplehimawari.ocnk.net
☆個人セッションも再開しました。
こちらも、ぜひ体験してみてくださいね。