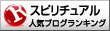古代日本ヒルコツアー 4 諏訪大社
前回の記事で、「土人形」の話を書きましたが、その続きです。
2018年4月下旬に、奈良県葛城市の当麻寺を訪れた時に、気づきがありました。
この寺には、金堂という建物がありました。

その建物の裏側には、何かを作っていたような痕跡が残っていました。
私は、この石で作られた置物が、とても気になりました。
ここで、何かを作っていたとしか思えなかったのです。

そして、この建物に中に、台も含め全身が土で作られた仏像があったのです。
つまり、「土人形」なのです。
建物内は撮影禁止ですが、ある方から特別に、建物内の仏像たちの写真を見せていただきました。

そして、この「土人形」たちの周囲を、木彫りの仏像が取り囲んでいたのです。
「四天王像」です。

まるで生きているような迫力でした。

この時に、根拠はありませんが、直観で、
「この土や木で作られた仏像たちは、昔、生命が吹き込まれて、動いていた時期があった」
こう思えたのです。
一般的な常識では、荒唐無稽かもしれませんが、私は、普段から、古代史を集中的に学んでいますが、こうやって、旅先でリラックスしている時に、面白い閃きが湧いてくることが多いのです。
「人形に生命が宿り、人間のように動きだす」
という話は、昔から世界中にあります。
有名なのは、「ピノキオ」ですね。
正式名は、「ピノッキオの冒険」で、イタリアの作家・カルロ・コッローディの児童文学作品で、1883年に最初の本が出版されて以来、100年以上にわたり読み継がれているそうです。

「くるみ割り人形」という作品も、見たことはありあませんが、そういう内容みたいです。
大昔には、こういう土や木から創られた人形に、生命を吹き込み、魂を宿すようなことを、たまにやっていたのではないでしょうか?
その代表的な儀式が、古代キリスト教などの「洗礼」だったのではないでしょうか?
ちょっと古いかもしれませんが、30年くらい前くらいに、ハリウッド映画に、「マネキン」という作品がありました。
中世のヨーロッパの御姫様が、魔法使いに魔法をかけれれて、マネキン人形にされてしましますが、現代に生まれ変わった王子様の魂をもつ男性のキスで、生き返るという話でした。
私は、これを観た時に大感動して、なぜか涙が出てきました。
この作品が、本当にあった話に思えて、しかたなかったのです。

わりと最近では、「ナイトミュージアム」という作品でも、夜中に、博物館に展示してある、化石標本や人形たちが、一斉に動き出し、朝になったら元の位置に戻り、何事もなかったかのように、また平静を装っているという場面が印象的でした。

現代の日本でも、子供向けの歌で、「おもちゃのチャチャチャ」とい歌詞の内容は、そういう話ですね。
もちろん、科学的には、ありえない話です。
しかし、私たち人間の科学は、万能ではありません。
未だに、地球が自転や公転している動力のメカニズムも、さっぱりわかっていないような状況です。
とても未熟で未完成なのが、現代科学なのです。
犬や猫などには、スマホの機能など、さっぱり理解できないと思います。
このように、人間には、未だに理解できないことなど、地球には、まだまだ山ほどあるのです。
本当に優秀な科学者たちは、こういうことを知っています。
だから、皆、謙虚なのです。
彼らの中には、超常現象をバカにする人はに、一人もいないと思います。
この世界は、基本的に、「何でもあり」なのです。
「人形に命が宿り、ある時間だけ動き回り、それから、また元の位置まで歩いて戻り、人形の姿に戻る」
こういう現象は、実際に肉眼で目撃した人は、とっても少ないと思いますが、だからといって、可能性はゼロではないのです。
そうです。
超科学、つまり、魔法を使えるような宇宙人や未来人、それから、神々と呼ばれている存在たちにとっては、朝飯前のことなのです。
そして、私たちからすれば、全く違う物質に見える、「筋肉」や「土」や「木」なども、神々からすれば、「素粒子」という全く同じもので構成されているように、見えるのかもしれません。
あとは、それぞれを、何らかのスーパーテクノロジーを使って、同じように動かすだけでいいのかもしれません。
子供の頃、女の子などが、「リカちゃん人形」を、本物の妹のように、大切に抱いたりしているのを見ても、特に、違和感は感じませんでした。
子供たちというのは、これらの「人形」に命が宿る可能性があることを、本能的に知っているのかもしれません。
興味深いのは、当麻寺から、ちょっと歩いた所に、「相撲館」という相撲の資料館があります。
なぜかというと、ここが、「相撲発祥の地」だと言われているからです。

「日本書紀」によると、紀元前23年7月7日、出雲の力持ち、野見宿禰が、大和の暴れ者、当麻蹴速と天皇の前で対戦して、勝ったと書かれています。
その時の当麻蹴速の塚が、この建物の近くにあるのです。
二人とも、力いっぱい戦い、宿禰が蹴速をたおします。
垂仁天皇はたいへん喜び、野見宿禰は領地をもらって、天皇につかえることになったそうです。
その後、野見宿禰の子孫は、埴輪や土器をつくる「土師氏」として活躍したとことです。

館内には、原寸大の土俵がありました。
私が、そこの土俵に立っている写真です。
「ハッケヨイ! ノコッタ!」

「相撲」は、日本だけでなく、実は、シュメール文明の頃にも行われていたようです。
遠く離れた砂漠の国、中近東でもあったというのは驚きですね。
これは、世にも不思議な土偶です。
壺を頭から被った二人が、相撲をとっています。
ちゃんと、マワシも穿いていますね。

私は、これを見て、またまた閃きました。
これは、神々が、土から人間を創った瞬間の場面だろうと思いました。
つまり、二つの壺を土俵に投げて、真ん中のあたりの空中で、壺の土がこぼれた瞬間、二人の土人形が現れて、そこで相撲を取り始めたのだと思うのです。
そういえば、「土俵」という単語の文字も、意味深ですね。
「土」+「人」+「表」=「土の人が表れた」
こういう意味になりますね。
つまり、太古の時代、当麻寺の近くでも、「人類創世」が行われた可能性が大きいということです。
そして、その壺の正体が、古代イスラエルの三種の神器の一つ、「マナの壺」だったのだろうと、思っています。
日本の丹後の地方の「眞名井神社」の「真名」の文字は、この「マナ」から名付けられたとも言われていますね。

前方後円墳とも同じ形ですね。

「人間は死んだら土にかえる」
「土から人間は創られる」
ここまで、この二つについて書きましたが、三つ目の話があります。
「人が死んだ後、土のまま生き返ることがある」
ということです。
つまり、死ぬはずだった土人形が、なんらかの誤作動で、再び蘇ることが、太古の時代には、頻繁にあったのかもしれません。
一番有名なのは、我が国の「古事記」に書かれていますね。
イザナギが黄泉の国に、死んだイザナミを探しに行くのですが、そこで醜い死体になった、ゾンビのようなイザナミが、追いかけてくるという話です。

なんと、古代においては、死んで土になったままの人間が、生き返って、生きている人々を襲ってくるという話が、すでにあったのです。
もしかしたら、日本においては、そういうことが多かったから、早いうちに、土葬の習慣を止めて、火葬にしたのかもしれません。
欧米諸国では、現在でも、「ゾンビ」の映画が多いですが、こういう映画を観て、私たちが、「怖い!」という恐怖を感じるのは、おそらく、前世において、こういう体験を、実際にやったからなのだと思います。

ちょっと前に、 マイケル・ジャクソンの「スリラー」という歌が、プロモーションビデオとともに、世界的に大ヒットしましたが、マイケルは、この世界の秘密を知っていたのかもしれません。

昔の中国にも、「キョンシー」がいましたね。
これも、そうだと思います。

もしかしたら、「ノアの大洪水」の話は、当時、地球全体の人間が、「ゾンビ」のようになり、大変な事態になったから、ノアの家族が、地球を支配していた神々に頼んで、洪水で、一掃してもらったのかもしれません。
どうしようもなくなって、地球のリセットをしたのが、あの大事件だったのかもしれないのです。

予備知識の復習も終わり、ウオーミングアップで温まってきたと思うので、そろそろ、本格的な旅行記に入っていきますね。
諏訪に着きました。
久しぶりに来ました。
12年ぶりくらいかな?
湖畔には、「モアイ」の形のオブジェがありましたが、「モアイ」は、実は、「アヌ王(アヌンナキの王様)」の姿です。

「諏訪大社 上社本宮」の鳥居です。

入口には、二つの木の絵がありました。
私は、ここは、世界中にたくさんあった、「エデンの園」の一つでもあり、二つの木は、それぞれ、「生命の木」と「知恵の木」だと思いました。

余談です。
ご存知のように、日本語の漢字は、英語などの「表音文字」と違い、「表意文字」です。
だから、文字そのものの中に、いろいろな意味を含んでいるものも多いです。
さらに、それが、「象形文字」だったりもするので、日本に住んでいて、子供の頃から、「漢字」に親しんでいると、自然と「絵心」のようなものが芽生えて、アートのセンスが磨かれるそうです。
だから、日本の漫画やアニメはレベルが高く、世界中で評価されているのだと思います。
聖書と漢字には、不思議な共通点が、あるようです。
たくさんあるのですが、いくつかを紹介します。
もちろん、全部仮説ですが、ユニークな視点だと思います。
〇「禁」=最初の人間である「アダムとイブ」の話を、表しているそうです。
「木」+「木」+「示」
の組み合わせですね。
聖書の中で、神が、アダムとイブに、
「一つの木からの実は食べてもいいが、二つ目の善悪の知識の木の実は食べてはいけない」
と言う場面がありますが、その部分みたいです。
「示」は、神に供える祭壇の象形文字だそうです。
「神が、二つの木を示している」
という状態らしいです。
「禁止」という言葉は、
「善悪の知識の木の前で止まる」
という意味かもしれません。
〇「歴」=「人が、二つの木の前で立ち止まってから、歴史がスタートした」
という意味らしいです。
「人」+「木」+「木」+「止」
という組み合わせですね。
〇「造」=最初の人間、「アダム」の意味だそうです。
「ノ(命)」+「土」+「口」+「しんにょう」
という組み合わせです。
聖書の中の記述、
「神が、最初の人間、アダムの体を地面の土から形造り、神の口から、命(ノ)の息が吹き込まれると、人は生きた者(ノ)となって、話したり(告)、歩く(しんにょう)ことが、できるようになった」
という意味だそうです。
〇「婪」=「イブ」を表していると言われています。
「林」+「女」
の組み合わせですね。
「二本の木の前にいる女」
だそうです。
「ラン」と、読みますが、
「むさぼる」、「際限なく、欲しがる」、「貪婪(どんらん)」
などの意味が、あるそうです。
〇「困」=食べてはいけない木の実を、口にしてしまい、大変さに気づいたアダムとイブは、
「困った事をした」
と、嘆いたようです。
「木の実を、口に入れる」
という文字だそうです。
〇「元」=「二」と、「儿(にんにょう)」の組み合わせです。
「儿」は、「人」の変形だそうです。
聖書では、人類の起源とは、二人の人間なので、これも、「アダムとイブ」を表しているようです。
「元は、二人の人だった」
ということですね。
〇「先」=これも、アダムを表しているようです。
「土」+「ノ」+「人」
の組み合わせで、
「土の人」
という意味ですね。
〇「船」=「ノアの大洪水」を生き延びた、ノアの家族を表しているようです。
ノアの家族は、八人でしたので、
「舟」+「八」+「口」
だそうです。
「その舟には、八つの口があった」
という意味だったかもしれません。
〇「洪」=これも、「ノアの大洪水」に、関係している文字みたいです。
「八人が、さんずい(海の意味かな?)を共にした」
という場面を表している文字かもしれません。
〇「乱」=聖書によると、ノアのひ孫、二ムロデが、バベルの塔を建造したそうですが、その目的は、神の真似をして、人々を一箇所に集めて、支配するためだったと言われています。
でも、その行為を怒った神は、人々の言語を混乱させました。
言葉が通じないので、同じ言語を話す者同士が、世界中に散らばって行き、二ムロデの支配は、失敗に終わったそうです。
それまでの言語は一つで、皆が、同じ言葉を話していたそうです。
バベルとは、「混乱」の意味もあるようです。
「人々の舌がミダレて、世界中に散らばった」
というのが、この文字の意味だそうです。
これも、ユニークな仮説ですね。
〇「王」=「三位一体」の意味だそうです。
「王」=「三」+「1」
の組み合わせですね。
〇「狂」=聖書の中の話、バビロンのネブカドネザル王を表しているそうです。
彼は、7年間、人々から追われ、雄牛のように草木を食べ、獣のような暮らしをしていたそうです。
「王が、獣に成り下がった」
という意味の文字だそうです。
「聖書と漢字」、不思議な関係が、たくさんありますね。
こういうのを勉強すると、楽しいでしょうね。
学校でも、教えないかな?
旅行記に戻ります。
これも、アヌンナキ一族のロケットの意味だと思います。

境内には、御神木がありました。

これは、有名な「御柱」ですね。

やはり、「相撲の土俵」がありました。

ここでも、四股を踏みました。

有名な力士の像までありました。

ここも、「人類創生」の聖地だったと思います。
そして、「太鼓」という打楽器は、人間を創る時に、その振動で、最初に心臓を動かすための道具だったような気がします。

友人のゆかさんとユカリさんです。
ランチのお蕎麦、美味しかったです。

ここから、ちょっと離れたところにある、「諏訪大社 下社秋宮」にも行きました。


ここの境内の建物は、「生命の木」の形に建てられているようです。
これは、友人のゆかさんが、発見しました。


記念撮影しました。

拝殿の前でも記念撮影しました。

龍の手水舎です。

「諏訪大社 下社春宮」です。

拝殿の前です。

この近くに、「万治の石仏」がありました。

「モアイ=アヌ王」ですね。


またまた、オマケの話題です。
最近、「アメリカ合衆国」という国家の裏の意味が、わかってきました。
歴史というのは、あまり変化しないシンボルを見ると、その本質がわかったりします。
アメリカのシンボルの一つに、「アメリカの国章」があります。
それには裏の意味がありました。

では、その裏の意味は、どうすればわかるでしょうか?
難しく考える必要はありません。
裏返しにすればいいのです。

裏返すと、あらあら不思議!
頭に羽飾りをしたインディアンの酋長が、後姿で立っている絵が出てきます。
裏返した国章の人物は、左手には矢を持ち、右手には榊を持っているようにも見えます。

この絵は、別の見方をすれば、ハワイ出身の力士が四股を踏んでいるようにも見えます。
外側の円は、土俵ですね〜

このことから、面白い仮説が出てきます。
「もしかしたら、アメリカ合衆国という国は、古代において、元々は日本がつくりあげた国だったかもしれない」
ということです。
面白いですね〜
そういえば、神社には、よく「矢」がありますが、不思議なことに、セットになるはずの「弓」がなかったりします。
だとしたら、その「矢」は、「特別な矢」だということです。

その「矢」は、エジプトの太陽神からの矢かもしれません。

そして、それは、宇宙から飛んできた「ウイルス」、つまり、「RNA」でもあったかもしれません。


「前方後円墳」でもあり、「アンク十字」でもありますね。



そういえば、近年、長野県の軽井沢では、ビルゲイツ氏が、自分別荘の中に、DNAの貯蔵庫を造ったという噂もありますね。
やはり、長野県には、何か不思議で特別なエネルギーがあるのかもしれません。
諏訪大社から、車でちょっと走った所にある、「神長官守矢史料館」にも、立ち寄りました。
入口には、「鹿」や「龍」の頭部を思わせる木がありました。

入口です。
「守矢」と書かれていますね。
これは、もしかしたら、「DNA(RNA)を守っている土地」という意味なのかもしれません。


館内には、壁に、たくさんの鹿や猪の首がありました。

生贄の復元展示ですが、初めて見ると不気味です。

私には、これらの「猪」と「鹿」が、「馬」と「鹿」の代用に見えました。
つまり、旅行記の最初に紹介した、「フォッサマグナ」を中心に分かれた、「馬」と「鹿」、つまり、「西日本」と「東日本」のシンボルに見えたのです。
つまり、「弥生」と「縄文」のシンボルだということです。
これについては、別の機会に詳しく書きますね。
諏訪地方には古代信仰、「縄文ミシャクジ信仰」というのがあり、巨石・大樹を神降し場とする信仰で、「ミシャクジ」を降神させる役目を担っていたのが、守矢氏(漏矢・のちに神長官だったそうです。
「ミシャクジ」という神様は、白蛇神だという説もあります。
私は、「ミシャクジ」という神様も、「ヒルコ」と関係があると考えています。

現代でも4月15日に催される、「御頭祭」がありますが、その昔は、神への奉納品として、鹿75頭、猪、兎、雁、鯉のほか海産物のアワビ、塩海老、ボラ、サメ、ヒダラ、タコ、ワカメなどがあったそうです。
酒は三石四斗余、土器1,000枚が用意されたそうです。
ちなみに、「75」という数字は、古代ユダヤにおいて、特別な数字だそうです。
私は、これらの無規則で、バラバラな奉納品からは、なんとなく、「魔法」を感じます。
つまり、中世のヨーロッパで、魔女たちが、魔法を使うときに、鍋に、「カエル」や「ネズミ」や「キノコ」や「薬草」などを入れて、煮込んだ場面が連想されるのです。
おそらく、現在でいう「遺伝子操作」、それから、「魔法の儀式」を、この土地で、やっていたのだと思います。
資料館の裏手、山側にある、「ミシャグチ神社(御頭御社宮司総社)」です。
これの詳しい説明についても、別の機会に改めてやりましょう。

記念撮影しました。

次回に続きます。
☆私の著書、「地球を創った魔法使いたち」も、絶賛発売中です。
ぜひ読んでみたください!
☆記事の感想などは、下記のアドレスに、お気軽にメールくださいね。(お手数ですが、メルアドは、コピーして貼り付けてください)
toma_atlas@yahoo.co.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
☆ランキングにも、参加しています。
記事が面白かったら、応援クリックもお願いします。
☆下記が、私のメインサイトの「精神世界の鉄人」のエッセイ集です。
不思議な体験談や精神世界の探求が、たくさん書いてあります。
現在は、ほとんど更新していませんが、遊びにいってみてくださいね。
http://www.tomaatlas.com/library.htm
☆フェイスブックもやっています。
☆インスタグラムもやっています。
☆ツイッターもやっています。
☆私が自信をもってオススメする、ヒーリンググッズの王様、「不思議なペンダント・アセンション」のサイトです。
http://triplehimawari.ocnk.net
☆個人セッションも再開しました。
こちらも、ぜひ体験してみてくださいね。