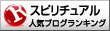人類創世マジカルツアー 3 人形
ここから先を読む前に、ちょっとだけ、書いておきたいことがあります。
ここからは、かなり頭の柔軟さが必要になってくるかもしれないので、頭をグルグルまわして、首周りの筋肉をほぐしてあげたり、腕をまわしたり、前屈運動や屈伸運動をして、全身の血流が、よく流れるようにしておくといいかもしれません。
首が、ゴキゴキなったり、腕や膝の関節が、ボキボキと音を出してる方も、多いかもしれませんね。
できれば、全身のストレッチ体操ができたら、ベストだと思います。
身体の柔軟性を頭の柔軟性は、ある程度は、関係しているみたいです。
最近、大学時代に読んだ本のことを思い出しました。
もうだいぶ前なので、詳しい内容は覚えていないのですが、当時は、明治大学の教授で、後に、政治家になった、栗本慎一郎さんの著書が、大好きで、よく読んでいたのですが、その中の一冊に、「縄文式頭脳革命」というタイトルの本がありました。
この本の中に、
「脳を集中状態にして、アルファ派を出しているような状態の時に、素晴らしいアイデアが浮かぶことが多い。しかし、そのアイデアには特徴があり、とても掘り下げられて深いのだが、視野が狭いことが多い。そこで、次の段階として、今度は、その思い浮かんだアイデアを、朝起きたばかりのウトウトしている意識状態の時に、再度放り込んでみる。この時は、脳波が自然に、シータ派になっているのだが、この時に、潜在意識が、そのアイデアを多角的に捉え、欠けている視点を教えてくれる」
というようなことが、書いてあったことを思い出しました。
簡単に言うと、
「集中してアイデアを出したら、その後、リラックスして、再度広い角度から、それを眺めてみなさい。そうすれば、もっと広がったアイデアが出てきますよ」
ということです。
この本は、すでに絶版になっていると思いますが、いわゆる、「天才脳」をつくる具体的なノウハウが書かれていました。
おそらく、太古の時代に、日本に来ていた、縄文人たちを支配していた宇宙人たちの脳が、そうやってつくられたことを、栗本先生は、なんらかの方法が、知ったのだと思います。
栗本先生自身が、大天才だと思いましたが、当時の私は、「本当の頭のよさ」というのに、憧れていたので、こういう自己啓発的な内容の本を、むさぼるように読んでいました。
その本の中には、興味深いことが、書かれていました。
「天才脳」には、二つの思考が必要で、まずは、集中して一つのことを、突き詰めるような状態が、大切だと書いてありました。
それには、肉体的には、大腿四頭筋を鍛えるのが効果的だと書かれていました。
欧米のインテリたちが、よく大学構内で、ジョギングをしたり、ジムに行って身体を鍛えるのは、本能的に、それを知っているからだそうです。
私は、これを知って、当時、やっていた、「パワーリフティング」という競技の中の「スクワット」という種目ばかりを、やるようにしたのが、懐かしい思い出です。
前述したように、そこで閃いたアイデアを、さらに、全身を脱力状態にしている時、特に、朝の寝起きの時に、ウトウトしながら、再考してみると、そのアイデアの欠けている点などに、気が付くことが多いとのことでした。
これを、繰り返すことによって、「狭くて深い視点」、それから、「広くて浅い視点」、この二つの視点が、融合してえ、「広くて深い視点」という、いわゆる、「天才の発想」というのが、生まれるとのことでした。
本当の天才の人たちは、自然に、この思考法を、繰り返しているのだそうです。
そして、一般の人々も、これをやれば、「天才脳」に近づけるという話でした。
私は、この思考法もいいのですが、いわゆる、「パネルディスカッション」という討論方法も、素晴らしい方式だと思っています。
これは、テレビの「朝まで生テレビ」などで、有名になりましたが、まず最初に、専門家だけで、とことん議論する。
そして、その後に、会場に来ている一般の人々にも、意見をきいてみる。
さらに、全国の視聴者からも、電話やFAX、e-mailなどで、幅広い意見を募集する。
これをやることによって、たくさんの人々の共同作業による、「広くて深い視点」が生まれるのです。
私は、現在でも、意識してこれをやっています。
今回の古代史においても、まずは、自分でとことん考えて、そのあと、古代史に詳しい友人たちと、意見交換をします。
さらに、それを、このように、ブログに書いて、たくさんの人たちから、さらに幅広い情報を提供してもらう。
この作業を繰り返すことによって、「とても広くて深い視点」が生まれるのです。
インターネットというのは、この作業をやるために、この世界に生まれたのだと思います。
では、これから、最高にワクワクする知の冒険に、出かけましょう!
前回の記事で、「土人形」の話を書きましたが、その続きです。
4月下旬に、奈良県葛城市の当麻寺を訪れた時に、また気づきがありました。
小雨の降る中で、寺の正面にある門を撮影しました。

この寺には、金堂という建物がありました。

その建物の裏側には、何かを作っていたような痕跡が残っていました。

私は、この石で作られた置物が、とても気になりました。
ここで、何かを作っていたとしか思えなかったのです。

そして、この建物に中に、台も含め全身が土で作られた仏像があったのです。
つまり、「土人形」なのです。
建物内は撮影禁止ですが、ある方から特別に、建物内の仏像たちの写真を見せていただきました。

そして、この「土人形」たちの周囲を、木彫りの仏像が取り囲んでいたのです。
「四天王像」です。

まるで生きているような迫力でした。

この時に、根拠はありませんが、直観で、
「この土や木で作られた仏像たちは、昔、生命が吹き込まれて、動いていた時期があった」
こう思えたのです。
一般的な常識では、荒唐無稽かもしれませんが、私は、普段から、古代史を集中的に学んでいますが、こうやって、旅先でリラックスしている時に、面白い閃きが湧いてくることが多いのです。
まさに、「縄文式頭脳革命」の思考法ですね。
こういう「人形に生命が宿り、人間のように動きだす」という話は、昔から世界中にあります。
有名なのは、「ピノキオ」ですね。
正式名は、「ピノッキオの冒険」で、イタリアの作家・カルロ・コッローディの児童文学作品で、1883年に最初の本が出版されて以来、100年以上にわたり読み継がれているそうです。

「くるみ割り人形」という作品も、見たことはありあませんが、そういう内容みたいですね。
大昔には、こういう土や木から創られた人形に、生命を吹き込み、魂を宿すようなことを、たまにやっていたのではないでしょうか?
その代表的な儀式が、古代キリスト教などの「洗礼」だったのではないでしょうか?
ちょっと古いかもしれませんが、30年くらい前くらいに、ハリウッド映画に、「マネキン」という作品がありました。
中世のヨーロッパの御姫様が、魔法使いに魔法をかけれれて、マネキン人形にされてしましますが、現代に生まれ変わった王子様の魂をもつ男性のキスで、生き返るという話でした。
私は、これを観た時に大感動して、なぜか涙が出てきました。
この作品が、本当にあった話に思えて、しかたなかったのです。

わりと最近では、「ナイトミュージアム」という作品でも、夜中に、博物館に展示してある、化石標本や人形たちが、一斉に動き出し、朝になったら、元の位置に戻り、何事もなかったかのように、また平静を装っているという場面が、印象的でした。

現代の日本でも、子供向けの歌で、「おもちゃのチャチャチャ」とい歌詞の内容は、そういう話ですね。
もちろん、科学的には、ありえない話です。
しかし、私たち人間の科学は、万能ではありません。
未だに、地球が自転や公転している動力のメカニズムも、さっぱりわかっていないような状況です。
とても未熟で未完成なのが、現代科学なのです。
犬や猫などには、スマホの機能など、さっぱり理解できないと思います。
このように、人間には、未だに理解できないことなど、地球には、まだまだ山ほどあるのです。
本当に優秀な科学者たちは、こういうことを知っています。
だから、皆、謙虚なのです。
彼らの中には、超常現象をバカにする人はに、一人もいないと思います。
この世界は、基本的に、「何でもあり」なのです。
「人形に命が宿り、ある時間だけ動き回り、それから、また元の位置まで歩いて戻り、人形の姿に戻る」
こういう現象は、実際に肉眼で目撃した人は、とっても少ないと思いますが、だからといって、可能性はゼロではないのです。
そうです。
超科学、つまり、魔法を使えるような宇宙人や未来人、それから、神々と呼ばれている存在たちにとっては、朝飯前のことなのです。
そして、私たちからすれば、全く違う物質に見える、「筋肉」や「土」や「木」なども、神々からすれば、「素粒子」という全く同じもので構成されているように、見えるのかもしれません。
あとは、それぞれを、何らかのスーパーテクノロジーを使って、同じように動かすだけでいいのかもしれません。
子供の頃、女の子などが、「リカちゃん人形」を、本物の妹のように、大切に抱いたりしているのを見ても、特に、違和感は感じませんでした。
子供たちというのは、これらの「人形」に命が宿る可能性があることを、本能的に知っているのかもしれません。
興味深いのは、当麻寺から、ちょっと歩いた所に、「相撲館」という相撲の資料館があります。
なぜかというと、ここが、「相撲発祥の地」だと言われているからです。

「日本書紀」によると、紀元前23年7月7日、出雲の力持ち、野見宿禰が、大和の暴れ者、当麻蹴速と天皇の前で対戦して、勝ったと書かれています。
その時の当麻蹴速の塚が、この建物の近くにあるのです。
二人とも、力いっぱい戦い、宿禰が蹴速をたおします。
垂仁天皇はたいへん喜び、野見宿禰は領地をもらって、天皇につかえることになったそうです。
その後、野見宿禰の子孫は、埴輪や土器をつくる「土師氏」として活躍したとことです。

館内には、原寸大の土俵がありました。
私が、そこの土俵に立ち、塩をまいている写真です。

「ハッケヨイ! ノコッタ!」

「相撲」は、日本だけでなく、実は、シュメール文明の頃にも行われていたようです。
遠く離れた砂漠の国、中近東でもあったというのは驚きですね。
これは、世にも不思議な土偶です。
壺を頭から被った二人が、相撲をとっています。
ちゃんと、マワシも穿いていますね。

私は、これを見て、またまた閃きました。
これは、神々が、土から人間を創った瞬間の場面だろうと思いました。
つまり、二つの壺を土俵に投げて、真ん中のあたりの空中で、壺の土がこぼれた瞬間、二人の土人形が現れて、そこで相撲を取り始めたのだと思うのです。
そういえば、「土俵」という単語の文字も、意味深ですね。
「土」+「人」+「表」=「土の人が表れた」
こういう意味になりますね。
つまり、太古の時代、当麻寺の近くでも、「人類創世」が行われた可能性が大きいということです。
そして、その壺の正体が、古代イスラエルの三種の神器の一つ、「マナの壺」だったのだろうと、思っています。
日本の丹後の地方の「眞名井神社」の「真名」の文字は、この「マナ」から名付けられたとも言われていますね。

前方後円墳とも同じ形ですね。

「人間は死んだら土にかえる」
「土から人間は創られる」
ここまで、この二つについて書きましたが、三つ目の話があります。
「人が死んだ後、土のまま生き返ることがある」
ということです。
つまり、死ぬはずだった土人形が、なんらかの誤作動で、再び蘇ることが、太古の時代には、頻繁にあったのかもしれません。
一番有名なのは、我が国の「古事記」に書かれていますね。
イザナギが黄泉の国に、死んだイザナミを探しに行くのですが、そこで醜い死体になった、ゾンビのようなイザナミが、追いかけてくるという話です。

なんと、古代においては、死んで土になったままの人間が、生き返って、生きている人々を襲ってくるという話が、すでにあったのです。
もしかしたら、日本においては、そういうことが多かったから、早いうちに、土葬の習慣を止めて、火葬にしたのかもしれません。
欧米諸国では、現在でも、「ゾンビ」の映画が多いですが、こういう映画を観て、私たちが、「怖い!」という恐怖を感じるのは、おそらく、前世において、こういう体験を、実際にやったからなのだと思います。

ちょっと前に、 マイケル・ジャクソンの「スリラー」という歌が、プロモーションビデオとともに、世界的に大ヒットしましたが、マイケルは、この世界の秘密を知っていたのかもしれません。

昔の中国にも、「キョンシー」がいましたね。
これも、そうだと思います。

もしかしたら、「ノアの大洪水」の話は、当時、地球全体の人間が、「ゾンビ」のようになり、大変な事態になったから、ノアの家族が、地球を支配していた神々に頼んで、洪水で、一掃してもらったのかもしれません。
どうしようもなくなって、地球のリセットをしたのが、あの大事件だったのかもしれないのです。

次回から、人類史における最大の秘密の扉を、ゆっくりと開いていきます。
心の準備はできていますか?
では、開きます。
ギッ、ギギギギ…
次回に続きます。
☆記事の感想などは、下記のアドレスに、お気軽にメールくださいね。(お手数ですが、メルアドは、コピーして貼り付けてください)
toma_atlas@yahoo.co.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
☆ランキングにも、参加しています。
記事が面白かったら、応援クリックもお願いします。
☆精神世界の面白いサイトが、たくさんあります。
http://airw.net/newage/rank.cgi?id=atlas
☆下記が、私のメインサイトの「精神世界の鉄人」のエッセイ集です。
不思議な体験談や精神世界の探求が、たくさん書いてあります。
2001年6月から、アメリカで書き始めたものです。
ぜひ、遊びにいってみてくださいね。
http://www.tomaatlas.com/library.htm
☆メインサイトです。
http://www.tomaatlas.com
☆フェイスブックもやっています。
☆インスタグラムもやっています。
☆ツイッターもやっています。
☆私が自信をもってオススメする、ヒーリンググッズの王様、「不思議なペンダント・アセンション」のサイトです。
http://triplehimawari.ocnk.net/